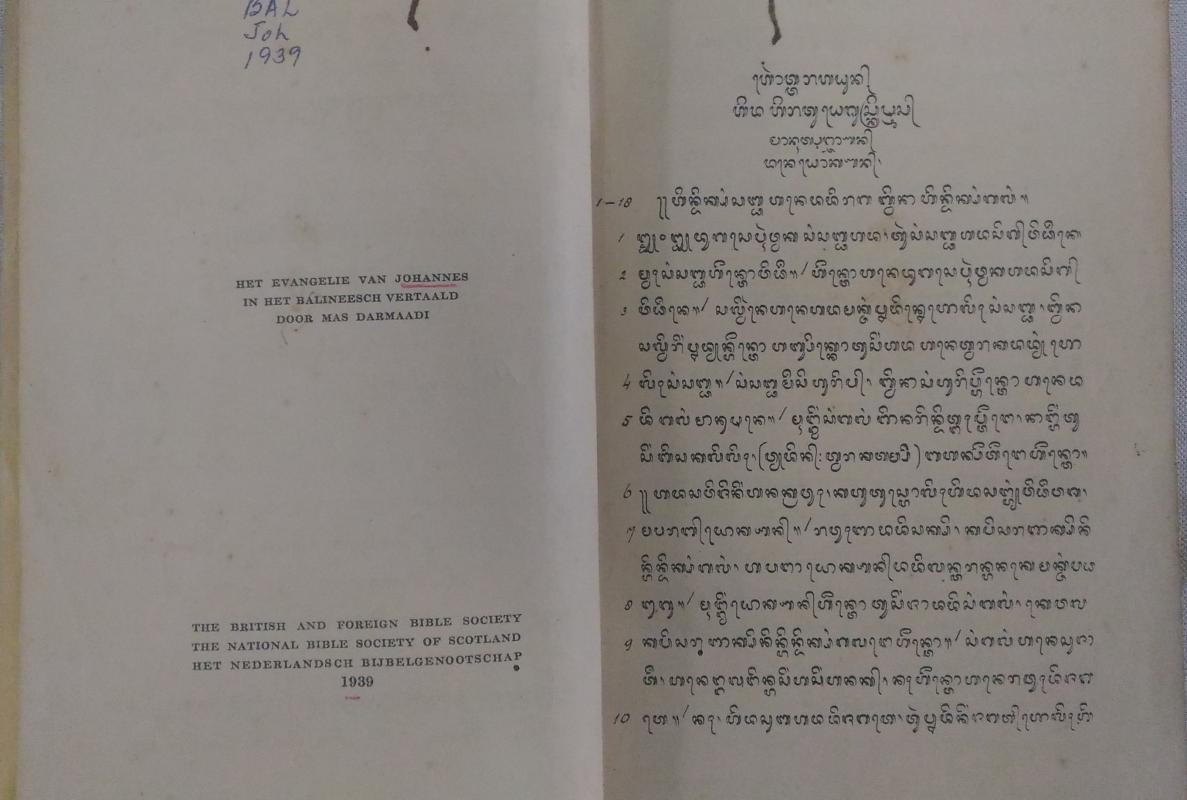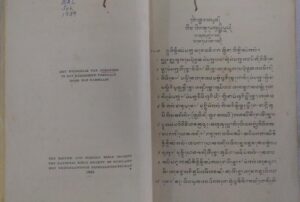
ヨーロッパでは、「未来」について語るのはあまり愉快なことではありません。経済は危機的で、政治には展望がなく、宗教にも希望をもてる余地があまりありません。世俗化の波が教会を覆いつくし、代わってイスラム教がヨーロッパ大陸の多数派宗教になるという人もいます。ましてや「聖書解釈の」未来を語ろうなど、ほとんど無意味に思われるかもしれません。
聖書を解釈する方法など、もうすでに言いつくされたことだと思う人もいるでしょう。さらには、世俗化のおかげで聖書はすっかり脇へ追いやられてしまい、とくに見るべきものもなく、せいぜい、とっくに時代遅れになった宗教を学ぶ道具にすぎない、とすら思われているようです。
聖書の権威が失われたのは、何も世俗化だけのせいではありません。聖書解釈の伝統の変遷も大いに関わっています。古典的なカトリックの視点では、聖書のテキストは、教会が作りだす教義に権威を与える基礎となるものです。何世紀にもわたって、新たな知識が作りだされ、その権威がもとのテキストに積み重ねられていきました。
リベラルなプロテスタントの視点でも、聖書のテキストそのものに権威があるわけではありませんでした。権威はむしろ、歴史批評の方にありました。テキストを審判する文化的・理論的枠組みこそが権威をもちました。やがて、テキストよりもテキストの今日的意義の方が重視されるようになり、そうこうしているうちに、テキストそれ自体を否定してしまったのです。
このような状況で、「原理主義」という解決法には希望のある未来を期待できません。それは、「本物の」信仰者なら科学文明と決別すべきだ、という一種の知的犠牲を求めるものでしょう。原理主義は、自らもまた聖書解釈の一つのプロセスであるということを無視しています。アンセルムス的な贖罪の理解、あるいはアルミニウス的な恵みの理解、あるいは19世紀のダーウィンへの反論、あるいは千年紀をめぐる現代の憶測を、これらが生まれた時代背景から切り離し、聖書の中につねに存在していた教理として一緒くたにするのです。
むろん、聖書を解釈する責任を自分で引き受けるよりも、宗教的に権威あるところに解釈してもらいたがる人々は、いつの時代もいるでしょう。一方、権威の濫用に幻滅して権威主義を否定し、支配的な文化と妥協して聖書より高い地位を与えてしまう人々もいます。そして、原理主義に安住し、一時的な人間の教理を、聖書が伝える永久不変の教えと混同する人々がいることも、自然のなりゆきでしょう。
しかし、これらは所詮、壁に囲まれたすき間に安住しているにすぎません。そこは未来に道を開くような聖書解釈がなされるところではないのです。
では導きをどこに求めるべきでしょうか。かつて再洗礼派が聖書に向き合った方法の中に、探求する価値のあるものがある、と私は考えます。それはどちらかといえば新しい方法に思われるでしょう。すでに提唱されてはいたものの、ほとんど実践されてこなかったからです。
言(ことば)の権威
なによりまず覚えるべきなのは、アナバプテストの観点からは、聖書解釈の権威は教会の権威でも、またカール・バルトのいう「紙の教皇」の権威でもない、ということです。権威は言(ことば)から、肉となった言(ことば)、メシアであるイエスご自身からくるのです。聖書解釈の前提は、見境なく受け入れることでも、文化的・疑似科学的に受け入れることでもなく、特定のテキストに権威を認めることです。聖書解釈の前提は、信じる者と主(しゅ)との間に出会いがおきること、その主こそイエスであるという告白がおきることです。
こうして、聖書がまずは相対的な性質をもつことが明らかになります。聖書は主イエスに対して相対的であり、主が聖書に対して相対的なのではありません。
これこそ、16世紀の初期再洗礼派が言ったことです。つまり、聖書はぶどう酒を入れる革袋であってぶどう酒そのものではない、と。聖書がぶどう酒そのものでないなら、そこに書かれたことは普遍的な教義マニュアルでも、他の普遍的な教義で置き換えられるべきものでもありません。むしろ、聖書に収められた教義はすべて、最上の言(ことば)であり、言(ことば)の性質を聖書に与える権威である、主を究極的に指し示すものなのです。
言(ことば)を指し示すもの
聖書が、キリスト・イエスを指し示す相対的なものであるということは、聖書解釈の未来にとってもう一つ重要な意味をもちます。それを「歴史実践性」とよぶことができるでしょう。復活した主と出会い、その権威を認めるということは、この主に従うための道具として聖書を用いる態度を導きます。再洗礼派がいう通り、主に従う生き方をしない限り主を知ることはできません。聖書は、神学の本である以前に、主に従うための手引書なのです。聖書にある、教義や世界観の要素を否定するのではなく、それらもまたイエスに従うことをつねに指し示していると捉えるのです。そしてこれは、あらゆる解釈につきものの、歴史的状況を反映した、実践的なプロセスです。
あらゆる解釈に実践的な性格が伴うということは、キリストのからだの一致のために、一定の謙虚さが当然必要になるということです。イエスに従う上で、私たちの聖書解釈は具体的な状況と結びつきます。状況は大切です。個々の教会の状況であれ、より広い文化的状況であれ、時代的な状況であれ、聖書のテキストはそれらの状況との関係で意味を帯びるのです。状況とのつながりを知ることは、解釈における霊的な側面を無視することではありません。むしろ、私たちを真理に導く聖霊もまた、歴史的な方法で、人々や状況や具体的な出来事を通して、私たちを導くということです。そうでないなら、そもそも私たちは聖霊を必要としないでしょう。いつの時代にも通用する、永遠の教義マニュアルがあれば十分だからです。
聖霊と言(ことば)
聖書解釈が霊的なプロセスであることは言うまでもありません。聖書を教義の体系と混同したり、聖書をより「近代的」な教義に基づいて評価したりすると、このことは忘れられがちです。
聖霊は思いのままに吹くものです。この「霊的な」自由こそ、イエスやパウロやヨハネが旧約聖書を読んだときに具体的に示した自由に他なりません。過去に定められた、確定的な意味を探すことから離れて、聖霊は新しい状況に基づく新しい意味の可能性を開き、死んだテキストを生きた言(ことば)へとよみがえらせるのです。
聖書解釈のプロセス
そういうわけで、聖書解釈のプロセスはつねに開かれたプロセスとなります。「確定的な」解釈を重んじるカトリックの視点ですら、同じ解釈に再検討を加えてきた歴史があります。聖書を不変の教義と捉える原理主義の視点ですら、過去の解釈を再検討したり新たな解釈を付加したりすることを避けられません。つまり、いかなる解釈も確定的であることを主張することはできないのです。
「明日はもっと明るくなるだろう」という初期再洗礼派の言葉があります。まさにそれゆえに、果てしなく積み重なる新たな解釈の澱(おり)に聖書が埋もれてしまうことはありえないのです。聖書があらゆる解釈に開かれているなら、確定的な解釈はなく、過去の解釈は相対化されます。そうすれば、おおもとの出来事に照らして、あらゆる歴史的経験が、その重要性にかかわらず、相対化されることになります。しかし、このおおもとの出来事とは、聖書を構成しているテキストのことではありません。おおもとの出来事とは、真正で確定的な神の言(ことば)であるキリストご自身です。
究極の規準
そういうわけで、開かれた聖書解釈は混乱を引き起こすものではありません。あらゆる聖書解釈には「究極の」規準があります。つまり、イエスご自身が確定的な神の言(ことば)である、ということです。聖書解釈を個人に任せてしまうことはできません。信徒はみな、同じ主と出会っています。その人たちの解釈を導くのは同じ聖霊です。
それゆえ、聖書解釈は再洗礼派がよく理解した通り、共同のプロセスです。確定的な権威あるところに譲り渡せるものでも、教会や国家に雇われているプロの神学者(あるいはインターネットで検索できる新たな解釈)に代わってもらえるものでもありません。
共同という理想
こうしてみてくると、共同の解釈というアナバプテストの理想は大きな将来性を秘めていると言えます。共同の解釈にとって、個々の教会は解釈の務めを第一義的に担うものとなり、人間や教会の権威はすべて、メシアの確定的な権威に従うものとして相対化されます。具体的な共同体による解釈であるからこそ、共同の解釈は一時的な壊れやすいものとして、少なくとも教皇や牧師や神学者よりは自分の限界を知るものとして、自らを位置づけます。共同の解釈は確定的でないこと、つねに学び続ける必要があることを自覚します。
それはまた、聖霊の必要をも自覚します。どんな解釈も、知識をもてあそんだり人気取りに走ったりしないためです。初期再洗礼派のように、むしろ共同体の一致した合意を求めるなら、解釈は開かれたプロセスとなり、私たちの将来にも不可欠なものとなるでしょう。それは、教派を超えるくらい広がりをもち、しかし真理を見失うことなく、イエスに従い、へりくだって神と共に歩むプロセスなのです。
—アントニオ・ゴンザレス・フェルナンデスはMWC平和委員会の委員。スペインの兄弟団の牧師。コイノニア神学センターの教師。
この記事は、2017年2月12日にアウグスブルク(ドイツ)でのリニューアル2027「み言葉により変えられる:アナバプテストの視点で聖書を読む」での講演より採録した。
Click here to read in English.